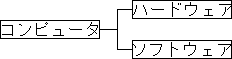 コンピュータというのは、大きく分けると、「ハードウェア」と「ソフトウェア」に分けることができる。
コンピュータというのは、大きく分けると、「ハードウェア」と「ソフトウェア」に分けることができる。
1944年 世界で最初のリレー式計算機「ASCC−MARK−I」の完成。
1946年 世界で最初の電子計算機「ENIAC」が完成。
1949年 世界で最初のプログラム内蔵方式の電子計算機「EDSAC」の完成。
(1946年頃にフォン・ノイマンがプログラム内蔵方式を提案する。)
1951年 世界で最初の商用計算機「UNIVAC−I」を作成。
1960年 日本で最初の商用計算機「NEAC2201」(日本電気製)を作成する。
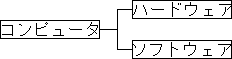 コンピュータというのは、大きく分けると、「ハードウェア」と「ソフトウェア」に分けることができる。
コンピュータというのは、大きく分けると、「ハードウェア」と「ソフトウェア」に分けることができる。
ハードウェアとは
コンピュータを構成している装置類のすべてのことをいう。例えば、家庭でも身近になっているパソコンでも、ディスプレイ」
「キーボード」・「プリンタ」・「本体」などがこれにあたる。
ソフトウェアとは
コンピュータというのは、ハードウェアだけがあっても何もやってくれない。それを働かせるのがソフトウェアである。ソフト
ウェアの代表的なものがプログラムである。
コンピュータは次の5つの基本機能から構成されている。
(1)記憶装置・・・プログラム・データ・計算結果などを記憶する装置のこと。
(2)入力装置・・・プログラム・データなどを入力する装置のこと。
(3)出力装置・・・実行結果などのデータを書き出したり、出力したりする装置のこと。
(4)演算装置・・・データに対して、四則演算などを実行する装置のこと。
(5)制御装置・・・記憶・入力・出力・演算装置を円滑に働くように制御する装置。
コンピュータというのは、それだけではただの箱というように、まったく動かないので、それを動かす為には、コンピュータに人間の意志を 伝えなければいけない。人間同士では言葉で伝えられるが、コンピュータと人間では言葉のかわりにプログラミングというものが必要である。この プログラミングというのはプログラミング言語で書かれている。
プログラミング言語には次のようなものがある。
(1)PASCAL
(2)FORTRAN(科学技術計算用)
(3)COBOL(事務処理用)
(4)BASIC
(5)C
フローチャート(流れ図)は、プログラムの処理手順を理解しやすいように図に示したものである。
フローチャートにもいろいろと種類があり、一般的なものにノイマン型フローチャートというのがある。
そのノイマン型フローチャートの基本処理記号や制御線をそのままにし、プログラムの視認性と記述性を飛躍的
に向上させて、格段に理解しやすくしたフローチャートに「Hichart」というフローチャートがある。
本コースウェアではPascalプログラミングと同時にHichartフローチャートの書き方についてもいっしょに示していく。
Hichartについて詳しく知りたい場合は、別のコースウェア「Hichart入門」を参照して下さい。
例)「ノイマン型フローチャート」と「Hichartフローチャート」の図
これからPascal入門を進めるにあたり、構文化する方法としてバッカス・ナウア記法を用いる。
バッカス・ナウア記法(BNF記法)というのは、J.W.BackusとP.NaurがALGOL60の構文を記述する
為に考えて出した記法である。
*約束ごと*